肺がんの化学療法・抗がん剤治療
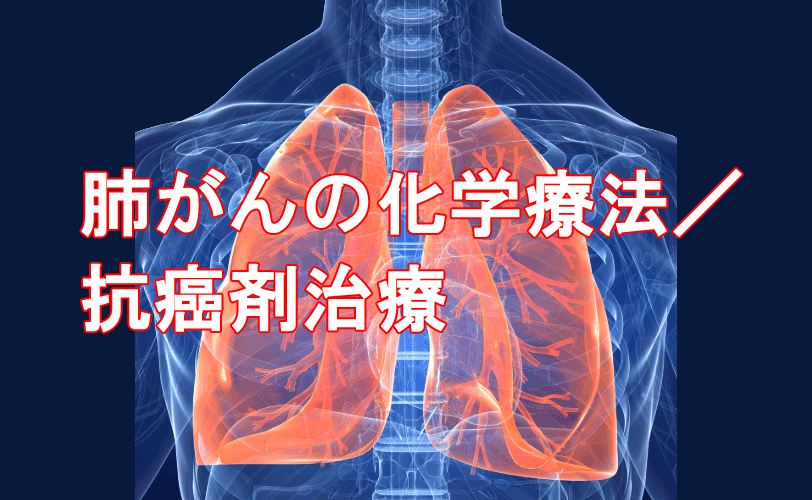
肺癌の治療法-肺癌の化学療法(抗がん剤治療)
肺癌の抗がん剤治療はどのような時に行われるのか
肺癌は進行すると周囲のリンパ節に転移し、さらに血流にのって反対側の肺や副腎、肝臓、骨、脳などに転移します。
肺癌の転移の可能性が極めて低い局所にとどまった癌である場合には手術や放射線療法による治療を行います。
しかし、リンパ節に転移があった場合や、転移は無くとも再発の危険が高いと判断された場合には抗がん剤療法が行われることがあります。
また、肺癌が肺内や副腎、肝臓、骨、脳など遠隔転移があり手術ができない場合にも化学療法(抗がん剤治療)が使われることがあります。
肺癌の組織型の違いによる化学療法(抗がん剤治療)
小細胞肺がん(小細胞肺癌)の化学療法
小細胞肺がんは極めて進行の早いタイプのがんであり、手術の適応となる事はまれですが、一方で放射線療法や化学療法(抗がん剤)には反応しやすいという点で他の肺がんとは異なった特徴を持っています。
小細胞肺がん(小細胞肺癌)の患者さんに化学療法(抗がん剤)を行うと、大凡80%程度の方に反応が見られるため、腫瘍は一時的に縮小することが期待できますが、根治は困難であり、再発してしまうケースがとても多いのが現状です。
使用される抗がん剤-小細胞肺がんの化学療法
 小細胞肺がんの化学療法では、シスプラチン+エトポシド(PE療法)、イリノテカン+シスプラチン(IP療法)、シクロホスファミド+ドキソルビシン+ビンクリスチン(CAV療法)などが代表的な抗がん剤の組み合わせになります。
小細胞肺がんの化学療法では、シスプラチン+エトポシド(PE療法)、イリノテカン+シスプラチン(IP療法)、シクロホスファミド+ドキソルビシン+ビンクリスチン(CAV療法)などが代表的な抗がん剤の組み合わせになります。
病状によっては、これらの抗がん剤の代わりにエトポシドやカルボプラチン、シクロフォスファミド、ドキソルビシンなどの抗がん剤を使用することもあります。
非小細胞肺がんの化学療法
非小細胞肺がん(腺がん(腺癌)、扁平上皮がん(扁平上皮癌)など)は抗がん剤治療の効果はあまり期待できません。
そのため早期の非小細胞肺がんで手術で癌を取りきれた場合、化学療法を行わずに経過観察することが多くなります。
非小細胞肺がんで化学療法が適応となるのは、臨床病期IIIB期あるいはIV期の進行例になります。
小細胞肺がんに比べると非小細胞肺がんは抗がん剤が効きにくく、腫瘍縮小効果が得られるのは20%~30%程度になります。また、一度効き目があった場合でもがんが耐性を持ってしまい次第に化学療法の効き目がなくなってしまうので、腫瘍縮小効果が認められたケースでも残念ながら根治は困難です。
非小細胞肺がんでは体力が低下している患者さんに抗がん剤治療をすると、抗がん剤の効果よりも体力を弱めて寿命を短くしてしまうことが懸念されます。一般に非小細胞肺がんの患者さんの場合、化学療法(抗がん剤治療)の効果が期待できるのはPS(全身状態)が0~2までの患者さんです。
使用される抗がん剤-非小細胞肺がんの化学療法
 非小細胞肺がんの化学療法では、プラチナ製剤とそれ以外の抗がん剤を組み合わせた治療が主流です。
非小細胞肺がんの化学療法では、プラチナ製剤とそれ以外の抗がん剤を組み合わせた治療が主流です。
具体的にはアリムタ+シスプラチン、イリノテカン+シスプラチン(IP療法)やシスプラチン+ビノレルビン、シスプラチン+ゲムシタビン、シスプラチン+ドセタキセル、シスプラチン+エトポシド(PE療法)、アリムタ+カルボプラチン、カルボプラチン+パクリタキセル、カルボプラチン+エトポシド(CE療法)などの組み合わせで治療が行われます。また、単剤ではパクリタキセル、ドセタキセル、ビノレルビン、ゲムシタビン(ジェムザール)などが代表的な抗がん剤になります。
<アリムタにより非小細胞肺がんの抗がん剤治療が変わりました>
アリムタは悪性中皮腫に有用性が認められた初めての抗がん剤ですが、2009年5月に切除不能な進行・再発の非小細胞肺がんにも適応が拡大されました。
アリムタが非小細胞肺がんに適応となるまでは、非小細胞肺がんの化学療法では薬剤の組み合わせによる有効性に大きな違いはなく副作用の出やすさなどによって使い分けをしてきました。
しかし、特に非小細胞肺がんの扁平上皮がん以外の患者さんでは、「ジェムザール+シスプラチン」と「アリムタ+シスプラチン」とでは「アリムタ+シスプラチン」の投与群の方が生存期間を延ばすという結果が得られたことから非小細胞肺がんの扁平上皮がん以外では「アリムタ+シスプラチン」が、それ以外の組織型では別の薬剤の組み合わせがすすめられることになります。
分子標的薬イレッサ(ゲフィチニブ)-非小細胞肺がんの化学療法
 非小細胞肺がんの治療ではイレッサという分子標的薬が2002年7月から使われるようになりました。
非小細胞肺がんの治療ではイレッサという分子標的薬が2002年7月から使われるようになりました。
イレッサは手術ができない、あるいは再発した非小細胞肺がんの治療薬として承認されています。
イレッサは吐き気や嘔吐、食欲不振や脱毛、骨髄毒性(白血球減少など)といった副作用は比較的出にくいのですが、肝機能障害や間質性肺炎などの副作用が出る傾向があります。
特に間質性肺炎は肺が線維化して硬くなり肺活量減少や酸素不足になるため、呼吸困難や咳、発熱などの症状から、悪化すると肺線維症という予後不良の状態になることがあります。一時期、イレッサによる間質性肺炎で死亡者が多く出たため社会問題化したことがありましたが、他の抗がん剤でも死亡する可能性が2%程度あり、決してイレッサだけが怖い薬ではないといえます。
イレッサについて詳しくはこちらを参考にしてください。
※他の抗がん剤も同様に怖いということを良く知っておかれた方が良いと思います。
分子標的薬タルセバ(エルロチニブ)-非小細胞肺がんの化学療法
タルセバ(エルロチニブ)はイレッサと同じようにEGFRと呼ばれる上皮増殖因子受容体をターゲットにした分子標的薬で、2007年から一般に使われるようになりました。
タルセバもイレッサと同じように手術ができない、あるいは再発した非小細胞肺がんの治療薬として承認されています。
イレッサやタルセバは、EGFRの細胞内の部分に取り付き、増殖の指令が伝わるのを抑える働きをし、EGFRチロシンキナーゼ阻害薬と呼ばれることもあります。
遺伝子に変異があるEGFRに情報伝達物質が結合すると、癌細胞の増殖は活発になりますが、このような場合にEGFRチロシンキナーゼ阻害薬であるタルセバやイレッサの効果が期待できるのです。
イレッサとタルセバはいずれもEGFRをターゲットとした分子標的薬です。
イレッサもタルセバも手術ができない、あるいは手術後に再発してしまった非小細胞肺がん(腺癌や扁平上皮癌)の患者さんに対し使用する分子標的薬ですが、ファーストライン(最初に選択される化学療法)は「プラチナ製剤+別の抗癌剤」になります。
タルセバについて詳しくはこちらを参考にしてください。
※他の抗がん剤も同様に怖いということを良く知っておかれた方が良いと思います。
分子標的薬ジオトリフ(一般名:アファチニブ)-非小細胞肺がんの化学療法
ジオトリフ(一般名:アファチニブ)はイレッサやタルセバと同様、癌細胞の増殖に関与する上皮成長因子受容体(EGFR)のチロシンキナーゼを選択的に阻害する薬です。
ただしイレッサ(ゲフィチニブ)やタルセバ(エルロチニブ)がチロシンキナーゼに対して可逆的に阻害する(一度チロシンキナーゼにくっつき阻害作用を示しても離れることがある)のと異なり、ジオトリフ(一般名:アファチニブ)は不可逆的に阻害作用を示します。
そのためイレッサやタルセバが第一世代の分子標的薬と呼ばれるのに対しジオトリフは第二世代の分子標的薬と呼ばれています。
イレッサ<タルセバ<ジオトリフの順で効果が期待できますが、一方で副作用もイレッサ<タルセバ<ジオトリフの順で強くなりますので、患者さんの全身状態などから治療効果と副作用のバランスを考える必要があります。
ジオトリフについて詳しくはこちらを参考にしてください。
※他の抗がん剤も同様に怖いということを良く知っておかれた方が良いと思います。
分子標的薬ザーコリ(一般名:クリゾチニブ)-非小細胞肺がんの化学療法
ザーコリ(一般名:クリゾチニブ)は分子標的薬ですが、イレッサやタルセバ、ジオトリフとは作用機序が異なります。
ザーコリカプセル(クリゾチニブ)は手術ができない、あるいは手術後に再発してしまった非小細胞肺がんの治療薬で癌の増殖に関与するALK融合タンパクを産生するALK融合遺伝子をもつ非小細胞肺がんに対して保険適応となっています。
事前検査でALK融合遺伝子がある事が確認された患者さんのみがザーコリ(クリゾチニブ)を投与することができます。
ジオトリフについて詳しくはこちらを参考にしてください。
※他の抗がん剤も同様に怖いということを良く知っておかれた方が良いと思います。
オブジーボ(一般名:ニボルマブ)-非小細胞肺がんの化学療法
オブジーボ(一般名:ニボルマブ)は一言でいうと「ヒトPD-1に対するヒト型IgG4モノクローナル抗体」であり免疫チェックポイント阻害剤です。
癌は免疫細胞の働きにブレーキをかけ免疫細胞の攻撃を阻止して自分たちを守っていますが、そのブレーキを解除し効かなくすることで免疫細胞の働きを再び活発にし、癌細胞を攻撃できるようにした薬です。
ジオトリフについて詳しくはこちらを参考にしてください。
※他の抗がん剤も同様に怖いということを良く知っておかれた方が良いと思います。
化学療法(抗がん剤)の副作用と効果判定
化学療法(抗がん剤)の副作用
骨髄毒性-白血球減少(好中球減少)、赤血球減少、血小板減少
 肺癌の抗がん剤治療により血液をつくる細胞がダメージを受け、白血球減少や赤血球減少、血小板減少などの副作用を高頻度で生じます。
肺癌の抗がん剤治療により血液をつくる細胞がダメージを受け、白血球減少や赤血球減少、血小板減少などの副作用を高頻度で生じます。
肺がんに対する化学療法では、患者さんが抗がん剤の副作用により死亡することが約2%程度起こると報告されています。治療関連死で最も多いのは白血球や好中球減少による重篤な肺炎や敗血症などの感染によるものですから、これらの血液検査の数値が低下した場合には注意が必要です。
白血球減少(好中球減少)が起きると肺炎などの感染症を起こしやすくなります。また発熱が続くこともあります。白血球や好中球の減少に対しては、G-CFS(顆粒球コロニー刺激因子)などを使用することがあります。
赤血球が減少することで貧血になったり、血小板減少により出血しやすくなったり、あざができやすくなったり、注射の跡が消えにくくなるなどの副作用が現れることがあります。
これらの副作用を骨髄毒性といいます。骨髄毒性は目に見える副作用ではないため一般の方は軽視しがちですが、実は命にかかわることが少なくない副作用ですから抗がん剤の投与中は注意深く骨髄毒性が許容範囲内であるかをチェックする必要があります。
吐き気・嘔吐・悪心・下痢・便秘・食欲不振
肺癌治療で抗がん剤が投与されると多くの方で吐き気や嘔吐をおこします。下痢や便秘をする方もいらっしゃいます。
使用する抗がん剤の種類により吐き気や嘔吐が起きやすい抗がん剤もあれば、あまり激しい副作用を伴わないものもあります。場合によっては極度の脱水症状により衰弱してしまう可能性もあります。
脱毛
肺癌治療で使用する抗がん剤によっては脱毛を起こすこともあります。治療が終われば髪の毛は再び生えてきます。
その他の副作用
肺癌治療で用いられる抗がん剤の副作用として、動悸や息切れ、体のむくみ、筋肉や関節の痛みなどが現れることがあります。
手足症候群といって手のひらや足の裏に刺すような痛みがあったり、手足の感覚がまひしたり、皮膚の乾燥やかゆみ、変色などの症状が現れることがあります。
口内炎や倦怠感(だるさ)、皮膚や爪の変色、味覚障害、肝機能障害、腎機能障害なども副作用で現れることがあります。
肺癌治療における化学療法(抗がん剤)の効果判定
化学療法(抗がん剤治療)を続けるか止めるか
抗がん剤の治療を行う際にの目的は「がんの縮小、そして延命」、「癌の進行を止める」「癌による痛みの軽減などQOLを改善する」などになります。
治療効果が十分で、副作用が軽微であれば治療を続けるメリットは大きいと思います。
一方で治療効果がなく、副作用が強く苦しみが増しているのであれば治療を続けることが患者さんにとって大きな負担となり、時に死期を早めてしまうリスクもはらんでいます。
抗がん剤治療を行う際には治療効果が得られているのか冷静に判断をすべきです。
また抗がん剤治療は体への負担が大きいため以下のPS(全身状態)を参考に治療を行う条件を満たしているかも確認が必要です。
以下に一般状態判定基準、効果判定基準を示しますので参考にしてください。
一般状態判定基準
| PS0 | 無症状で日常生活に支障のないもの |
|---|---|
| PS1 | 症状はあるが、日常生活に支障のないもの |
| PS2 | 就床を必要とするが、日中50%以上の日常生活が可能と考えられるもの |
| PS3 | 日常生活は可能であるが、日中50%以上就床を必要とするもの |
| PS4 | 1日中ほとんど離床不能なもの |
※一般にPS0~3が化学療法治療対象となるが、PS3は予後が悪いことが多く薬剤感受性の良い腫瘍やPS2に近い3の症例に限った方が安全である。
治療の効果判定
| CR(著効) | 腫瘍が全て消失した状態が4週間以上継続している。完全寛解ともいう。 |
|---|---|
| PR(有効) | 腫瘍が50%以上(半分以上)縮小している状態が4週間以上継続している。 |
| NR(不変) | 効果がPRには満たない、あるいは、増悪が以下のPDに当てはまらない。すなわち、腫瘍の縮小が半分にまで至らないか、25%以内の増大におさまっている。 |
| PD(進行) | 腫瘍の25%以上の明らかな増大。あるいは他の病変の出現・増大 |
※一部の腫瘍が縮小した場合でも、他の部分が新たに出現あるいは増大した場合には進行と判断します。
-
前の記事
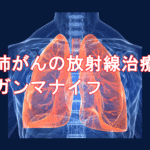
肺癌の放射線療法・ガンマナイフ
-
次の記事
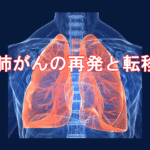
肺癌の再発/肺がんの遠隔転移
